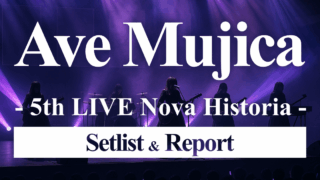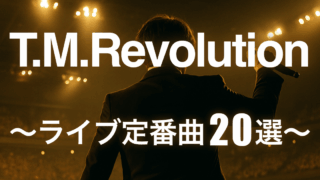◇ 声が枯れるまで歌った!WANIMA(ワニマ)ライブで欠かせない20曲

ライブの幕が上がった瞬間、空気が一気に変わる。WANIMAのライブは音楽を“聴く場”ではなく、観客が全身で参加し、汗と声で完成させる「体験」そのものだ。イントロが始まると自然に拳が突き上がり、サビでは大合唱が広がる。隣にいる初対面の観客と肩を組んで笑い合うことも珍しくない。筆者自身も何度もその場に立ち会い、喉が枯れても構わず叫び、涙と汗でぐしゃぐしゃになりながら「生きている」と実感してきた。
その熱気を支えるのが、繰り返し演奏される定番曲の存在である。データを見ても、2023〜2025年のライブで頻繁に披露されてきた楽曲は決まって観客と強く結びついている。「BIG UP」や「いいから」はイントロで爆発的な盛り上がりを作り出し、「ともに」ではサビの大合唱で会場がひとつになる。「エル」では照明が落ち、青白いライトに包まれて会場全体が静寂に沈む瞬間が訪れる。そして「Japanese Pride」ではKENTAの「Shake! Shake! Shake! Japanese!」の声に合わせて、フロア中が拳を突き上げる。これらは単なる人気曲ではなく、ライブを構成するうえで欠かせない役割を持つ。
SNSやYouTubeのコメントでも「声が枯れるまで歌った」「泣きながら笑った」といった感情が多く残されており、実際の観客体験と一致している。筆者も同じように、声を限界まで張り上げたり、涙が込み上げたりする瞬間を何度も味わった。
本記事では、直近のセットリストの傾向をもとに筆者自身の体験を掛け合わせ、WANIMAのライブに欠かせない20曲を徹底的に紹介する。読者の中には「セトリでよく演奏される曲を知りたい」という人もいれば、「ライブ前に予習しておきたい」という人、さらには「現場で味わった熱をもう一度思い出したい」という人もいるだろう。この記事はそのすべてのニーズに応えることを目的としている。
WANIMAの音楽は、笑顔の後に涙がこぼれ、静寂の直後に爆発する――そんな感情の振れ幅を体験できるのが大きな魅力だ。繰り返し演奏される曲には必ず理由がある。盛り上げ曲から涙を誘うバラードまで――ここで取り上げる20曲は、WANIMAのライブを語るうえで絶対に外せない存在だと断言できる。
◇ WANIMA(ワニマ)ライブ&フェスのセトリ定番曲20選

- 眩光
- BIG UP
- いいから
- ともに
- Hey Lady
- THANX
- オドルヨル
- 1106
- 雨あがり
- 1988
- Cheddar Flavor
- エル
- Revenge
- JOY
- 夏暁
- ここから
- LIFE
- 月の傍で
- Oh⁉︎ lie! wrong‼︎
- Japanese Pride
1. 眩光
WANIMAのライブにおいて、ここ数年でクライマックス前後に欠かせない定番曲となったのが「眩光」だ。演奏が始まると同時にステージと客席の熱が一気に高まり、眩い照明が曲名そのままの光景を作り出す。筆者も実際にその場に立ち、まるで夜空に大輪の花火が打ち上がったかのような光と熱に包まれて胸が高鳴ったのを覚えている。
歌詞には背中を押してくれるような前向きなメッセージが込められている。サビの「目を覚ます 決めた方角追いかけて」というフレーズは、迷いや不安を振り切って自分の道を進む勇気を与えてくれる。ライブではこの言葉に呼応するように観客が拳を突き上げ、会場全体がひとつに繋がる瞬間が訪れる。その光景は、単なる楽曲披露ではなく「生きる力を共有する体験」そのものだと筆者は感じた。
2. BIG UP
WANIMAの楽曲の中でも、大人の恋愛や男女の関係を思わせる少しきわどい歌詞が特徴的な1曲が「BIG UP」だ。落ち着いたテンポにタイトなリズムが重なり、独特の色気と挑発的なムードを漂わせている。普段のWANIMAの明るいイメージとは一味違い、その遊び心と大胆さに思わず笑みがこぼれる瞬間がある。聴き慣れたファンはもちろん、初めて触れる人にとっても印象に残る楽曲だと感じた。
ライブではサビの「BIG UP! BIG UP! BIG UP!」の掛け声で観客全員が声を張り上げる瞬間が訪れる。筆者もその場で我を忘れ、全力で叫びながら拳を突き上げた。会場全体が揺れるほどの熱気は、まさにWANIMAのライブならではだ。フェスでもワンマンでも後半の定番として組み込まれることが多く、**一気に会場を解放し、クライマックスへ導く“アダルトな盛り上げ役”**として存在感を放っている。
3. いいから
WANIMAの楽曲の中でも、ひときわアダルトで挑発的なニュアンスを放つのが「いいから」だ。直接的な言葉選びは、大人の恋愛や衝動を思わせる生々しさを持ち、音源で聴くだけでもインパクトがあるが、ライブでその勢いはさらに増幅する。
イントロ(シントロ)が鳴り響いた瞬間、観客の間から自然に「ヘイ!ホー!」の掛け声が広がる。筆者もその声に背中を押されるように拳を突き上げ、体が勝手に反応していた。サビに入ると今度は「Wow wow wow」と全員での大合唱に変わり、ステージとフロアの熱がぶつかり合って一気に爆発する。
周囲の観客と肩をぶつけ合いながら声を張り上げていると、音楽と観客の熱気が混ざり合い、フロア全体がひとつの塊になって動いているのを肌で感じた。ライブの中盤から終盤にかけてピークを作り出すこの曲は、まさにWANIMA流の“攻めの定番”だと筆者は実感した。
4. ともに
イントロが鳴った瞬間、会場の空気がふっとやわらかく変わった。KENTAの声が響くと、心の奥に直接語りかけられているようで胸が熱くなる。歌詞に込められた「どんな状況でも前へ進もう」というメッセージは、迷いや苦しみを抱えた自分の背中を押してくれるように感じた。
サビでは観客全員が声を合わせ、ステージとフロアがひとつに繋がる大合唱となる。筆者もその中で夢中になって叫びながら歌い、気づけば隣にいた知らない人と肩を組んでいた。涙ぐむ人、笑顔で声を張り上げる人、そのすべてが同じ歌に心を重ねている光景は忘れられない。
「ともに」は、WANIMAのライブに欠かせない絶対的な定番曲だ。世代や立場を超えて観客をひとつにするその力は、単なる人気曲ではなく「ライブを象徴する存在」だと筆者は強く実感した。
5. Hey Lady
わずか1分弱という短さながら、WANIMAらしい勢いと遊び心が凝縮された一曲が「Hey Lady」だ。軽快なカッティングギターと跳ねるようなビートが始まった瞬間、会場の空気が一気に切り替わり、フロアのテンションは最初から最高潮へと引き上げられる。
ライブでは「Ah Yeah Ah Ah」のシンガロングが自然に沸き起こり、観客の声と熱気がステージにぶつかるように広がっていく。筆者も体が勝手に反応し、声を張り上げて叫びながらジャンプしていた。短い時間にもかかわらず、その熱量は他の曲に引けを取らない。
フェスでもワンマンでも序盤に配置されることが多く、「開幕のスイッチ」を確実に入れてくれる存在だ。この曲が始まった瞬間、観客全員がひとつになり、ライブが本格的に動き出すのを肌で感じる。まさにWANIMAが放つ開幕宣言と呼ぶにふさわしい。
6. THANX
「THANX」は、WANIMAのライブにおいて感謝とエールをまっすぐに届ける定番曲だ。キャッチーで覚えやすいメロディに乗せて響く「ありがとうを込めて歌ったこの気持ちに嘘はないと」という歌詞は、聴く人の心の奥深くに届く。迷いや不安で立ち止まったときにも、そっと背中を押してくれる応援歌として、多くのファンに支持されてきた。
ライブでこの曲が始まると、サビでは自然に観客の歌声が重なり、会場全体が大きな合唱に包まれる。筆者もその瞬間ばかりは我を忘れ、胸の内にある感情を吐き出すように声を張り上げた。大きな声で歌ううちに、不思議と心が軽くなり、ステージとフロアの間に見えない温かさが広がっていくのを感じた。
フェスでは夕暮れどきに披露されることが多く、オレンジ色の空に歌声が響く光景
7. オドルヨル
イントロでワウを効かせたギターが鳴り響いた瞬間、体が自然に揺れ出すのを止められなかった。激しいビートに飲み込まれ、気づけば周囲の観客と一緒にジャンプしていた。曲の途中でリズムが切り替わる展開では、会場全体がクラップで応える光景が広がり、そのグルーヴに身を委ねるしかなかった。
歌詞に込められた「夜を思い切り遊び尽くす感覚」と、汗だくで踊るフロアの姿が完全にシンクロする。ステージ上ではミラーボールが回転し、無数の光を振り撒きながら空間全体をきらめかせる。筆者もその光の渦に包まれながら、解放感に身を投げ出すように声を張り上げた。
気づけば息が切れて、体中が汗で濡れていたが、心の中には「まだ終わってほしくない」という高揚感が残っていた。「オドルヨル」は、WANIMAのライブでしか味わえない“遊び尽くす夜”を体現する1曲だと改めて感じた。
8. 1106
静かなイントロが流れた瞬間、会場の空気が一変し、ざわめきがすっと消えていった。KENTAの歌声はまるで手紙を読み上げているかのようで、言葉ひとつひとつが胸に真っ直ぐ届く。歌詞に込められた“ありがとう”の気持ちを受け取るたびに、自分も大切な人の顔を思い浮かべていた。
サビに差しかかると、KENTAが声を振り絞る姿に胸を揺さぶられ、涙腺が崩壊しそうになるほどの強い感情が込み上げた。観客も声を出すのではなく、呼吸を合わせるように静かに聴き入る光景が広がり、ステージとフロアの境界がなくなっていくように感じられた。
曲の終盤では、会場全体が優しさと温かさに包まれ、その場にいた全員の想いがひとつに重なる瞬間が訪れた。筆者にとって「1106」は、ただのバラードではなく、WANIMAの音楽が持つ「人と人をつなぐ力」を象徴する特別な存在だと、改めて心に刻まれた。
9. 雨あがり
勢いのあるギターが鳴り響いた瞬間、体が自然と前へ突き動かされた。荒々しいビートに乗せて放たれる歌詞は、「どんな傷を抱えていても明日は切り開ける」と語りかけてくるようで、胸の奥に小さな火が灯るのを感じた。
サビに入る頃には観客全員が拳を掲げ、会場全体がひとつの声になって響く。その光景はまるで雨雲が晴れて、虹がかかる瞬間のように一気に明るさを取り戻していく。筆者も声を張り上げながら拳を突き上げ、重たい気持ちが吹き飛んでいくのを確かに体で感じた。
汗で視界がにじんでも、周りには笑顔が溢れていた。「雨あがり」は、落ち込んだ気持ちを音楽と熱で塗り替えてくれる、WANIMAのライブならではの再生のアンセムだと強く実感した。
10. 1988
タイトル「1988」がステージに映し出された瞬間、自分の中でも特別なスイッチが入ったような感覚があった。KENTAの生まれた年を冠した楽曲だと知って聴くと、歌詞に込められた“歩んできた道”への想いがより強く胸に響いてくる。
ミドルテンポのビートに身を任せながら自然と拳を突き上げていると、懐かしさと未来への力強さが同居するサビのメロディが広がり、胸の奥がじんわりと熱を帯びた。音源で聴く以上に、ライブではその言葉と音が観客一人ひとりの記憶と重なり合い、会場全体を大きな物語で包み込んでいく。
筆者自身も、この曲を聴いたとき「彼らの物語を自分も共有している」と感じた。「1988」は単なる新曲ではなく、WANIMAの過去と現在、そして未来を繋ぐ象徴的な一曲だと強く実感した。
11. Cheddar Flavor
ライブの幕が上がり、最初に鳴り響いたのがこの曲だった。分厚い3ピースサウンドが会場を包み込み、体が一瞬で持っていかれる。気づけば自然にジャンプしていて、スタートから全身が熱を帯びていた。
この曲はコロナ禍の時期にリリースされたこともあり、FUJIの力強いドラムとKENTAの歌声から伝わる**「ここからまた始めよう」というメッセージ**が、より強く胸に刺さる。音源で聴く以上に、ライブではその決意が観客一人ひとりに直に届いてくるように感じた。
イントロから会場全体が一斉に跳ねる光景は圧巻で、続く楽曲への期待感を一気に高めてくれる。短い時間で会場のギアを一段も二段も上げる力を持つ「Cheddar Flavor」は、WANIMAのライブの始まりを飾るにふさわしい一曲だと筆者は実感した。
12. エル
会場の照明がすっと落ち、静かにイントロが鳴り始めた瞬間、胸を締めつけられるような感覚に包まれた。KENTAの声は震えるほど真っ直ぐで、喉を振り絞るように放たれる歌に思わず息を呑む。音源で聴いたときよりも何倍も激しく響くサウンドが、逆に切なさを際立たせ、心の奥深くに突き刺さってきた。
観客は声を出さず、ただ耳を傾けて涙ぐみながら頷く。筆者も同じようにその一音一音を受け止めながら、言葉にできない感情に揺さぶられていた。サビに差しかかる頃には、ステージとフロアの空気が重なり合い、共有している想いがひとつになる瞬間が訪れる。
「エル」は、WANIMAのライブの中でも特別な位置を占める曲だ。熱狂の渦の中にこうした静けさと切なさがあるからこそ、ライブ全体の振れ幅がより深く心に刻まれる。ライブでこそ本当の意味で響く楽曲だと筆者は強く感じた。
13. リベンジ
イントロが鳴り響いた瞬間から、全身が震えるほどの迫力に包まれる。「Revenge」は攻撃的なビートに乗せて、冒頭から観客の声を引き出す一曲だ。AメロやBメロの合間には「Oh Yeah!」「Fire!」「Wow wow wow」といったコールが絶え間なく飛び交い、ステージとフロアの掛け合いが途切れることなく続く。
サビに入ると、KENTAの歌声に呼応するように観客全員が「Try Try Try!」「辛い辛い辛い!」と叫ぶ。その声の波が押し寄せ、会場全体を飲み込む熱気が生まれる。筆者も拳を突き上げながら全力で声を合わせ、心の奥にあった悔しさやモヤモヤを吐き出すように叫んだ。
その瞬間、楽しさと高揚感が一気に倍増し、会場がひとつの塊になる感覚を味わった。「Revenge」はまさに、ライブでしか体験できない圧倒的な一体感を生み出す象徴的な曲だと筆者は感じている。
14. JOY
イントロの軽快なリズムが鳴り出した瞬間、会場の空気が一気に明るく切り替わった。タイトルの通り“喜び”を全身で表すように、観客が左右に揺れながら自然と笑顔になっていく。その雰囲気に飲み込まれるように、筆者自身も表情が緩み、体がリズムに合わせて動き始めた。
サビに入ると、声を合わせて歌う観客が増え、フロア全体がジャンプの波に包まれる。自分も夢中で飛び跳ねながら声を張り上げ、気づけば周囲の見知らぬ人たちと笑顔を交わしていた。音楽を通じて繋がる瞬間の温かさに、胸がいっぱいになったのを今でも覚えている。
KENTAが歌う表情と、それに応える観客の笑顔が重なった光景は、ライブでしか見られない最高のシーンだった。辛いことや日常の重さを忘れ、とにかく楽しさだけを共有できる――「JOY」は、WANIMAの“みんなで楽しむライブ”を象徴するアンセムだと実感した。
15. 夏暁
イントロが流れた瞬間、夏の朝を思わせる清々しい空気が会場を包み込んだ。これまでの聴き慣れたコードとは少し違う響きに、新鮮な高揚感が体の中へ広がっていく。歌詞に込められた「絶望の中で小さな光を見つけた」というメッセージは、筆者自身の胸にも深く突き刺さり、薄暗かった未来にかすかな希望が灯るのを感じた。
サビの「Here we go, going up」に差しかかると、観客も拳を突き上げながら声を合わせる。会場全体が一斉に前を向くエネルギーに満ちていく光景は、WANIMAのライブならではのものだ。筆者もその渦中で声を張り上げ、心が再び動き出す瞬間を全身で体感した。
「夏暁」は、夜明けを迎えるような爽快感と、そこに滲む切なさが共存する楽曲だ。ライブで聴くことで、希望へ向かう気持ちを強く呼び起こしてくれる――そんな存在だと筆者は実感している。
16. ここから
イントロの勢いあるギターが鳴った瞬間、背中を強く押されるような感覚が走り、自然と拳が突き上がった。「ここからまた始めよう」という真っ直ぐなメッセージが心に刺さり、これまで抱えていた迷いや不安が一瞬で吹き飛ぶのを体感した。
サビでは観客全員が声を合わせて大合唱となり、会場中に前を向くエネルギーが充満していく。その渦の中で筆者も声が枯れるほど叫びながらジャンプし、気づけば涙と汗で顔がぐしゃぐしゃになっていた。
「ここから」は、ただ盛り上げるだけでなく、再スタートを象徴する曲としてライブに欠かせない存在だ。自分の中に眠っていた力を呼び起こし、「もう一度踏み出せる」と思わせてくれる。WANIMAのライブで必ず聴きたい、希望の原点となる一曲だと筆者は感じた。
17. LIFE
イントロの爽やかなギターが鳴った瞬間、胸の奥から熱がこみ上げてくるのを感じた。「LIFE」に込められているのは、迷いや葛藤を抱えながらも「それでも前へ進める」という、生きることそのものへの肯定だ。そのメッセージが音とともに広がり、心の奥深くまで真っ直ぐに響いてきた。
サビに入ると会場全体が大合唱となり、KENTAの声と観客の声が重なり合って大きなうねりを生み出す。筆者もその中で喉が枯れるのも構わず声を張り上げ、涙を流しながら笑顔で歌っていた。声を合わせるたびに、自分の中の不安や迷いが少しずつ剥がれ落ちていくようだった。
「LIFE」がライブで響くとき、そこにいる誰もが困難を越えていけるような気持ちになる。生きる力を与えてくれる、まさにタイトル通りの一曲だと、筆者は心から実感した。
18. 月の傍で
静かなイントロが始まった瞬間、会場全体の空気がやわらかく変わった。照明が落ちて、ステージに青白い光が差し込むと、まるで月明かりの下に立っているかのような幻想的な雰囲気に包まれる。
KENTAの声は切なさと温かさを同時に持ち合わせ、歌詞に込められた“寄り添う気持ち”が真っ直ぐ届いてきた。サビに入ると、観客は大きな声を出さず、静かに口ずさむように歌いながらステージとフロアを優しく繋いでいく。筆者も胸がじんわり熱くなり、その時間に身を委ねていた。
激しい曲の合間にこのような静けさが訪れるからこそ、ライブ全体の振れ幅が際立つ。「月の傍で」は、会場に一瞬の安らぎと温もりを与える存在であり、WANIMAのライブをより深く印象づける楽曲だと筆者は実感した。
19. Oh⁉︎ lie! wrong‼︎
イントロから加速していくビートに胸が一気に高鳴る。シンプルでありながらクセになるリフが鳴り響いた瞬間、フロア全体がジャンプの波で揺れる光景が広がった。
特に印象的なのはシンガロングで、観客全員が「ヘーイ!ヘーイ!!!」と叫ぶ瞬間だ。ステージとフロアが完全に噛み合い、熱気が一気に広がっていく。筆者も拳を突き上げながら声を張り上げ、その勢いに飲み込まれていった。
サビにかけて加速するテンションは留まることを知らず、気づけば声も体力も奪われている。それでも「まだ叫びたい」と思わせるほどの高揚感がある。「Oh!? lie! wrong!!」は、ライブをさらに熱くするスパイスのような存在であり、WANIMAらしい一体感を極限まで引き出す1曲だと筆者は実感した。
20. Japanese Pride
イントロから放たれる重厚なサウンドが響き渡った瞬間、会場全体がざわめきに包まれた。日本人としての誇りやアイデンティティを真っ直ぐに歌い上げる歌詞は、自然と背筋を伸ばさせる力を持っている。
KENTAが「Shake! Shake! Shake! Japanese!」と声を放つたびに、観客は拳を突き上げ、全力のレスポンスで応える。サビに入るとフロア全体が大合唱となり、まるで国歌のように一つの大きな声で響き渡った。その音の波に飲み込まれ、筆者も夢中で叫びながら胸が熱くなるのを感じた。
その瞬間、会場にいる全員が国境や世代を越えて仲間になったような一体感に包まれていた。「Japanese Pride」は、ライブ終盤に演奏されることが多く、心の奥から力を呼び覚ますWANIMAの象徴的な一曲だと筆者は実感している。
◇ まとめ:WANIMA(ワニマ)のライブは「声」と「体験」でひとつになる
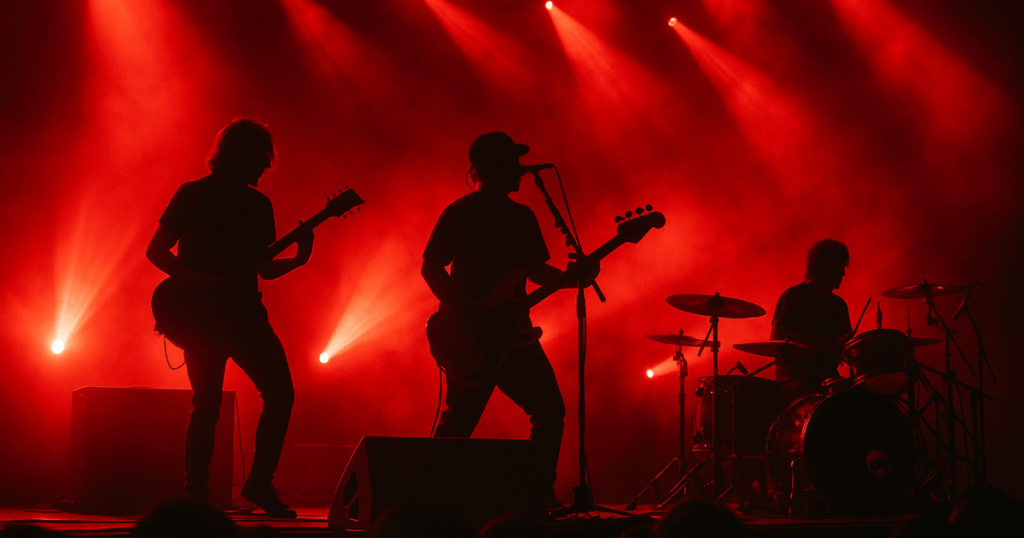
WANIMAのライブは、ただ音楽を“聴く”時間ではなく、観客とバンドが一体となって作り上げる体験そのものだ。イントロが鳴った瞬間から拳が突き上がり、サビでは会場全体が大合唱に包まれる。笑顔で叫んだ直後に涙がこぼれることもある――そんな振れ幅の大きな感情を共有できるのが、WANIMAのステージの特別さだ。
全員で歌う大合唱の曲
「ともに」はWANIMAの代名詞として世代を超えて歌われ続けている。サビで観客全員が肩を組んで大合唱する光景は、ライブを象徴する瞬間だ。また「Japanese Pride」の「Shake! Shake! Shake! Japanese!」という掛け声も、国境や世代を超えて誰もが声を合わせられる場を生み出している。こうした楽曲は、データ上の演奏回数が変動しても、ライブの核として常に組み込まれている。
会場を爆発させる盛り上げ曲
「BIG UP」「いいから」「オドルヨル」といった曲は、イントロの一音でフロアを爆発させる力を持つ。SNSやYouTubeのコメント欄には「声が枯れるまで叫んだ」「隣の人と肩を組んで歌った」といった体験談が並び、観客全員で楽しむ“フェス的アンセム”として機能していることがよく分かる。
涙を誘う感動曲
一方で「エル」「1106」「雨あがり」などのバラードは、会場全体を静かな涙で包む時間を生み出す。全力で声を張り上げた後に訪れる静けさと涙――その落差こそがWANIMAのライブを唯一無二のものにしている。実際に2023〜2025年の演奏データを見ても、こうした緩急のある楽曲構成は欠かさず組み込まれている。
初めての人にも、何度も通う人にも
初めてライブに行く人は、この20曲を押さえておけば安心だ。シンガロングや掛け声のポイントを少しでも予習しておけば、現場で自然に声が出て、楽しさは倍増する。一方で、すでに何度も足を運んでいるファンにとっては「みんなで泣いた」「全力で叫んだ」という記憶を呼び起こしてくれる。
◇ よくある質問(FAQ)
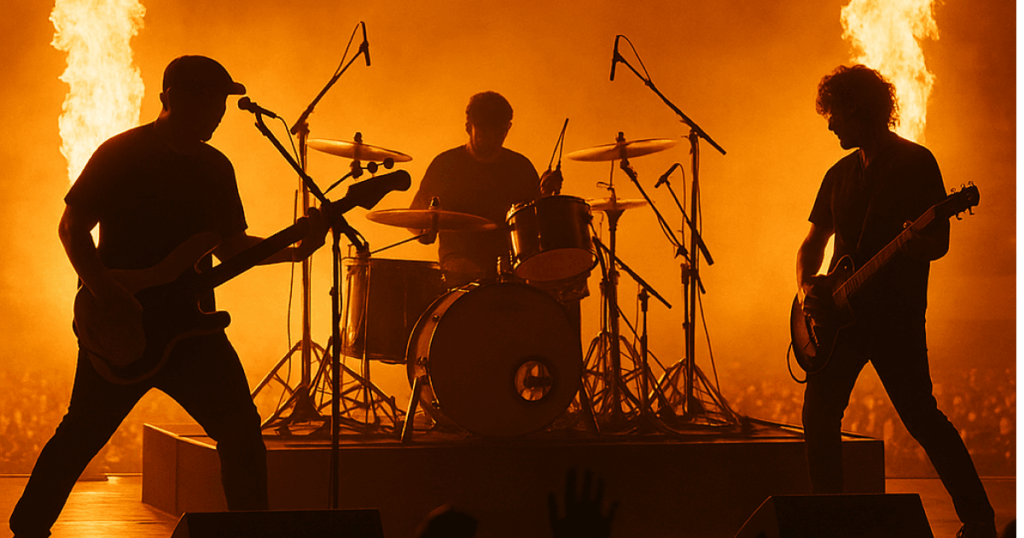
Q1. WANIMAのライブで必ず演奏される曲は?
A. セトリは公演ごとに変わりますが、「ともに」「BIG UP」「いいから」「眩光」「Japanese Pride」 は演奏頻度が高く、定番として期待できます。
Q2. 初めてWANIMAのライブに行く場合、予習すべき曲は?
A. 盛り上がり重視なら「BIG UP」「いいから」「ともに」。涙を誘う感動系なら「ともに」「エル」「1106」。これらを押さえておけば、自然にシンガロングできて楽しさが倍増します。
Q3. WANIMAのライブの雰囲気は?
A. 一言で言えば「全員参加型」。拳を突き上げ、コール&レスポンスで声を合わせ、時には笑って叫び、時には涙を流す――音楽と観客の境界線がなくなるのが特徴です。
Q4. フェスとワンマンでセトリは違う?
A. 違います。フェスは短い持ち時間のため「BIG UP」「いいから」「Japanese Pride」など盛り上げ曲中心。ワンマンでは「エル」「1106」「雨あがり」のようなバラードも組み込まれ、感情の振れ幅がより大きくなります。
Q5. シンガロングや掛け声は覚えていった方がいい?
A. 覚えておくと楽しさが倍増します。たとえば「Revenge」では観客が「Try Try Try!辛い辛い辛い!」と叫び、「Japanese Pride」では「Shake! Shake! Shake! Japanese!」が定番。「ともに」ではサビを全員で大合唱するのが鉄板です。
◇ WANIMA(ワニマ)公式サイト・各種SNS一覧

- WANIMA公式サイト
- X(旧Twitter)
- YouTube