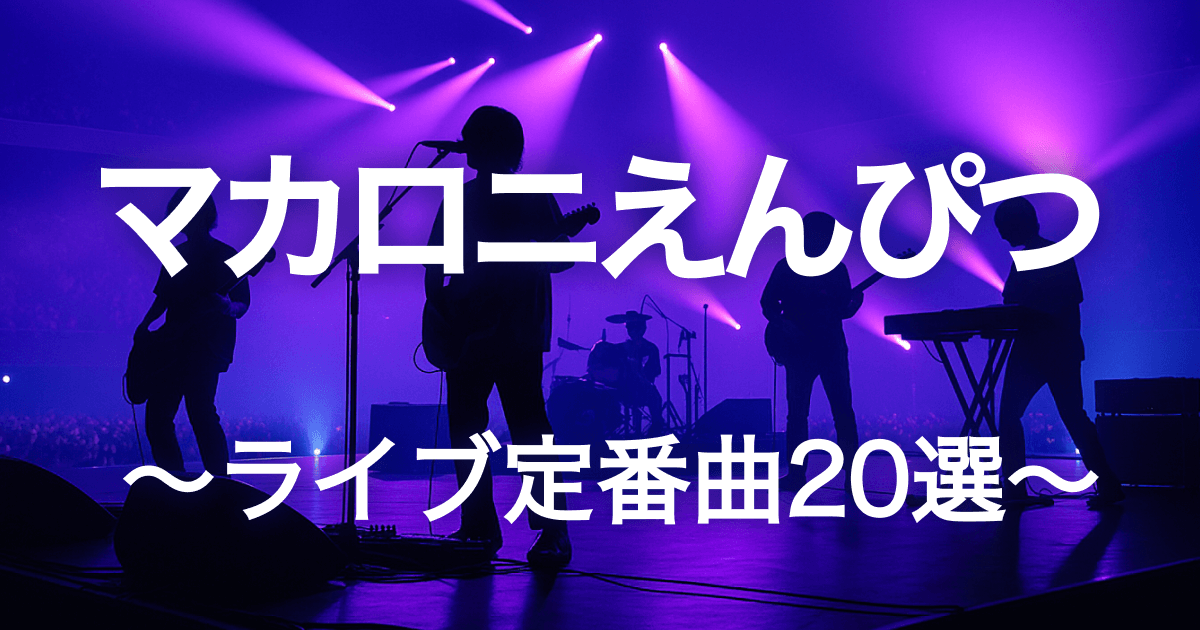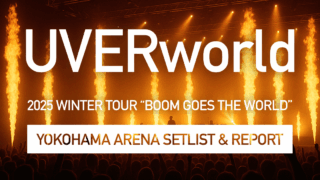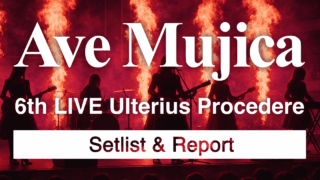この記事でわかること
- マカロニえんぴつ ライブ&フェスのセトリ定番曲20選
- 各曲の“現場で刺さるポイント”を曲ごとに解説
- 読み方:まず曲リスト→刺さった曲から個別解説へ
◇ なぜマカロニえんぴつ(マカえん)のライブは“歌詞が響く”のか?
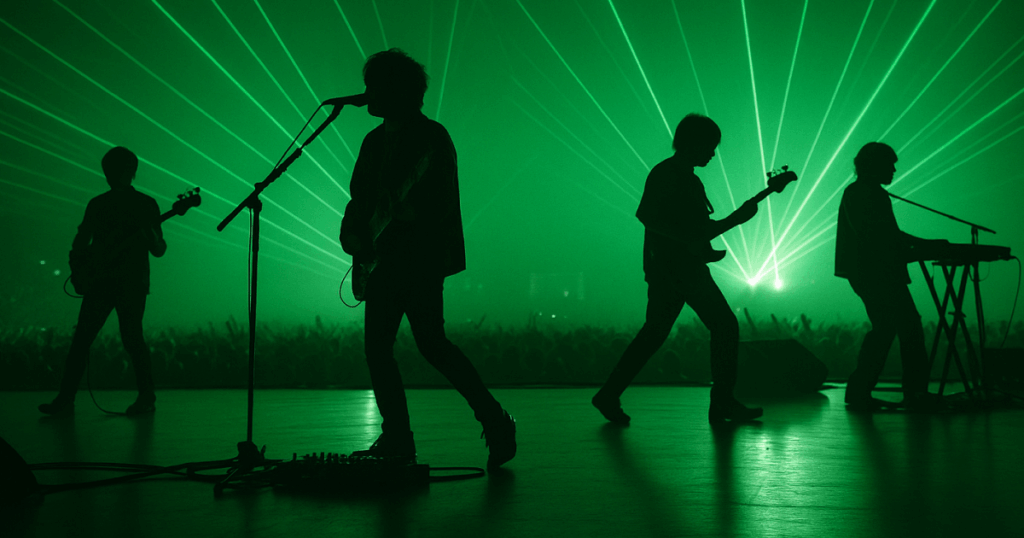
マカロニえんぴつ(マカえん)の歌は、ただのラブソングでは終わらない。失恋の痛みや、人間関係のもどかしさ、日常の小さな希望までを丁寧に切り取る歌詞は、聴く人の心を強く揺さぶる。そしてライブで披露されたとき、その歌詞は音源以上の説得力を帯び、会場全体に共有される体験へと昇華するのだ。
筆者が初めて彼らのステージを体感したときに驚いたのは、観客がまるで自分の物語を歌うように、歌詞を一緒に口ずさんでいたことだ。「なんでもないよ、」のサビでは数万人が合唱し、“大切な人を思い出しながら歌っている”空気がフロア全体を包んでいた。単なるシンガロングではなく、それぞれの人生に寄り添う歌詞だからこそ自然に声が出る。
一方で、「恋人ごっこ」や「悲しみはバスに乗って」のようなバラードでは、誰も声を出さず、ただ歌詞に耳を傾けて涙を流す観客の姿がある。静寂の中で音楽だけが響き、“一人ひとりが自分の記憶と向き合っている”ような空間が生まれるのだ。
もちろん盛り上げ曲も忘れてはいけない。「レモンパイ」や「洗濯機と君とラヂオ」では、歌詞の一節に合わせて観客が声を返し、拳を突き上げる。特に「どうせ何百回も」のあとに〈会いに行く支度する!!〉と叫ぶあの一体感は、歌詞が“参加するための合図”として機能している瞬間だと感じる。
こうした振れ幅こそがマカロニえんぴつのライブの醍醐味だ。同じバンドの中に、泣けるバラードと爆発的なロックチューンが共存し、そのどちらにも歌詞が強烈な意味を持っている。観客は曲ごとに表情を変え、泣いて、叫んで、また静かに聴き入る。その繰り返しがライブ全体を大きな物語のように感じさせる。
本記事では、そんなマカロニえんぴつのライブで定番となっている20曲を、最新セットリストをもとに厳選した。歌詞がどんな瞬間に響き、観客がどう反応するのか。実際のレポートや体験談を交えながら、**「ライブで必ず聴いておきたい名曲たち」**を紹介していく。
他アーティストの“セトリ定番曲”もまとめて見たい人はこちら。
◇ マカロニえんぴつ(マカえん)ライブ&フェスのセトリ定番曲20選|予習におすすめ
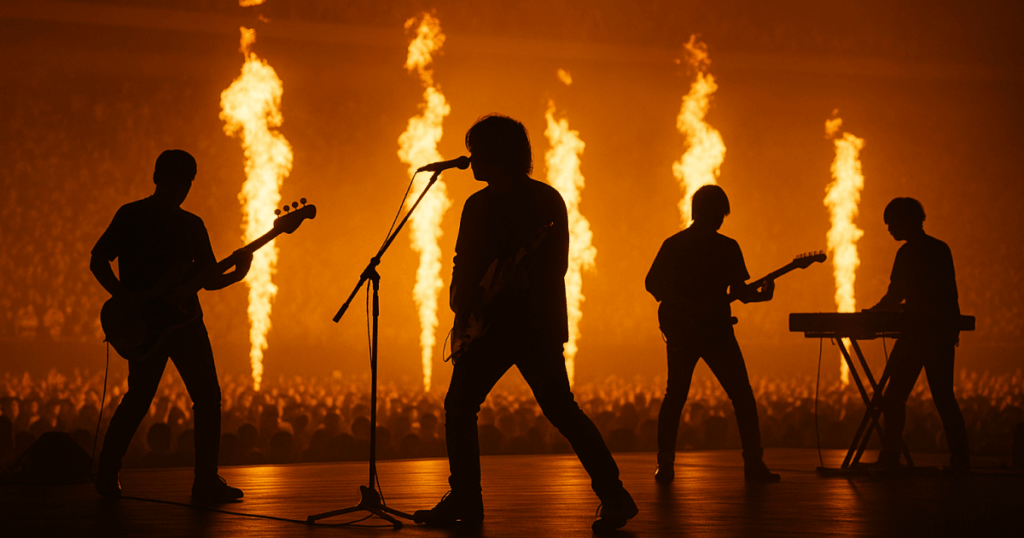
- なんでもないよ、
- レモンパイ
- 洗濯機と君とラヂオ
- リンジュー・ラヴ
- 恋人ごっこ
- 悲しみはバスに乗って
- 星が泳ぐ
- ヤングアダルト
- ブルーベリーナイツ
- 魂の居場所
- ハートロッカー
- Enshin
- 月へ行こう
- 忘レナ唄
- poole
- Route 16
- 然らば
- Mr.ウォーター
- 恋のマジカルミステリー
- だれもわるくない
1. なんでもないよ、
『なんでもないよ、』は、バラードでありながらライブで最も大合唱が起きる定番曲だ。筆者が聴いたステージでも、1番サビに入った瞬間に客席が一斉に歌い出し、まるで会場全体が合唱団になったような光景に鳥肌が立った。観客が涙を浮かべながら歌詞を口にする姿はSNSでも数多く報告されており、「隣の人と一緒に歌って泣いた」といった感想も多い。アーティストが「みんなで一緒に」と呼びかけると、数万人の声が重なり空気が震える。その一体感は**“ただ聴く”を超えた共有体験だ。演奏後には「超いいね!」と笑顔で声を返すやりとりも恒例で、会場には信頼を表す手拍子と歓声が広がる。静寂に浸る曲が多いバラードの中で、この曲は声を出すことで涙と熱狂が同居する特別な時間**を作り出している。
2. レモンパイ
『レモンパイ』は、イントロが始まった瞬間に会場を跳ね上げる夏の定番曲だ。筆者が体感したライブでも、「どうせ何百回も」の直後に観客全員が〈会いに行く支度する!!〉と大声で叫び、フロアが震えるほどの熱気に包まれた。この掛け声はSNSやライブレポでも「絶対に声を合わせたくなる名場面」として語られる鉄板ポイントで、初参戦の観客も自然に巻き込まれる。サビ前後ではジャンプとクラップが同時に広がり、観客とバンドが完全にシンクロする一体感が生まれる。フェスでは広大な空の下で腕を振り上げる光景が夏らしい爽快感を倍増させ、ワンマンでは序盤の“爆上げ曲”として会場を一気に温める役割を担う。音源のポップさに対し、ライブではビートが太く迫力を増し、**「ライブ文化を象徴するアンセム」**として強く根付いている。
3. 洗濯機と君とラヂオ
ライブ序盤で空気を一気に変える定番曲が『洗濯機と君とラヂオ』だ。イントロが始まると手拍子が自然に広がり、力強いサウンドに観客の声が重なる。特にサビ前、はっとりがマイクを向けると〈この恋が この恋が その声で…〉と観客が大合唱する光景は、多くの公演レポートやSNSでも「合唱大会のようだった」と語られる鉄板シーンだ。間奏からサビにかけては“歌わせる”パートが続き、ミドルテンポに合わせてクラップが走る。終盤では声量がさらに増し、歓声と手拍子が重なって会場は最高潮に。ワンマンでは序盤の盛り上げ役、フェスでは観客参加型の目玉として配置されることが多く、ファンの間でも「これは絶対に歌う曲」と認知されている。
4. リンジュー・ラヴ
アップテンポでキャッチーな『リンジュー・ラヴ』は、イントロから観客の体を揺らし手拍子を誘う“跳ね曲”だ。筆者が聴いたステージでも、自然とリズムに合わせて笑顔が広がり、フロアの空気が一気に軽やかになった。特にサビ前、ボーカルが「りんご飴って言ってくれる?」と投げかけると、〈あげるよ、残りの林檎飴〉と返す大合唱が恒例で、SNSでも「この掛け合いで一体感が最高潮に達した」と語られている。観客が跳ねながら歌詞を返す光景は、夏祭りさながらの陽気さで会場を包み、笑顔と歓声が交錯する時間となる。一方でドラマ主題歌としての“聴かせる一面”もあり、サビ前の緊張感やアウトロでのため息まじりの拍手など、盛り上がりと感涙の両方を併せ持つのも特徴。ライブの中で必ず色を変えてくれる稀有なナンバーだ。
5. 恋人ごっこ
バラード調でありながら圧倒的な存在感を放つ『恋人ごっこ』は、披露された瞬間に会場の空気を一変させる。筆者が体感したステージでも、はっとりが感情を込めて歌い出すと客席は水を打ったように静まり、声を漏らすことなくじっと耳を傾けていた。SNSやレポートでも「噛みしめるように聴き入った」「涙を堪えられなかった」との声が多く、観客の心を一瞬で支配する力を持つ曲だ。サビの「僕は君の恋人じゃない」では、抑えきれない感情が口ずさみとなって自然に客席から漏れ出すことも多い。意図的なコールではなく、感情が声になってしまう場面がこの曲の特異性だ。演奏後はしばし余韻が漂い、やがて温かな拍手が包み込む。序盤〜中盤のキラーチューン枠として定番化しており、爆発的な盛り上がりではなく**“静寂と共鳴で心を結ぶ”**マカロニえんぴつらしいバラードである。
6. 悲しみはバスに乗って
情感たっぷりの大バラード『悲しみはバスに乗って』は、イントロが流れた瞬間に会場の空気を一変させる。筆者が体感したステージでも、観客が一斉に声を潜め、まるで別世界に迷い込んだような静けさが広がった。サビに入ると照明や演出が幻想的に切り替わり、はっとりの深みのある歌声が重なると涙を拭うファンも多い。SNSでも「反則級に心を揺さぶられた」「無言で聴き入るしかなかった」といった声が目立ち、“歌わせる”ではなく“聴かせる”側の曲であることがわかる。サビ終わりには温かな拍手が自然と起こり、演奏終了後には大歓声が湧くのが定番だ。セットリストでは中盤の“景色替え”として組み込まれることが多く、アップテンポな流れを落ち着かせ、しっとりとした余韻を会場に残す。マカロニえんぴつの持つエモーショナルな側面を象徴する一曲だ。
7. 星が泳ぐ
**ライブ終盤を彩るハイライト『星が泳ぐ』**は、静かなイントロから徐々に盛り上がり、ラストに向けて感動が最高潮に達する一曲だ。演奏が始まると会場は一気に静まり、観客は夜空を見上げるように照明に見惚れながらじっと聴き入る。サビに入るとはっとりのロングトーンに合わせて歓声が波のように広がり、涙を拭う人も多い。SNSでも「歌詞と景色が重なった瞬間に胸が震えた」「泣きながら聴いた」といった声が多く寄せられており、決まったシンガロングがなくても自然に感情が会場を支配するのがこの曲の特徴だ。終盤に置かれることが多く、静けさと爆発が交互に訪れる構成は、物語のクライマックスを形作る。照明や演出が夜空を思わせる中で、観客は最後まで夢中になり、会場全体が一体となって高揚感を共有する瞬間を作り出す。
8. ヤングアダルト
**アンセミックなメロディが胸を突き刺す『ヤングアダルト』は、アンコールや終盤に配置されることが多い“心を持っていかれる代表格”**だ。筆者がライブで体感したときも、希望と哀愁が入り混じる独特の空気に包まれ、会場全体が静かに引き込まれていった。サビの「夜を越えるための唄が…」では自然と拍手が重なり、小さく歌詞を口ずさむ声が客席のあちこちから漏れ出す。決まったコールがあるわけではないが、音楽に導かれるように発生するシンガロングやため息混じりの歓声が、この曲特有の共鳴を生む。SNSでも「聴きながら泣いてしまった」「背中を押された気がした」といった感想が目立ち、万人規模の会場でも共感が波のように広がることが多い。終わった瞬間に胸の奥が熱くなる——そんな余韻を残してくれる、マカロニえんぴつのライブ定番だ。
9. ブルーベリーナイツ
ファンにとって特別な意味を持つ『ブルーベリーナイツ』は、イントロが流れた瞬間に会場中から大歓声が沸き起こる愛され曲だ。筆者が体感したステージでも、冒頭のオルゴール音とピアノリフが鳴った途端に期待感が一気に広がり、観客の顔に笑みが浮かんだ。演奏が始まれば歓声と手拍子が自然と重なり合い、グルーヴィーなサウンドに合わせて体を前のめりに揺らす観客の姿があちこちで見られる。決まったコールはないものの、ラストのフレーズで自然にシンガロングが起きやすいのが特徴で、締めの三連発に配置されることも多い。SNSやレポートでも「この瞬間に立ち会えてよかった」「感情が溢れた」との声が多く、演奏後にはファン同士で余韻を共有する光景も見られる。叙情的な世界観に包まれた余韻が長く続き、マカロニえんぴつのライブを象徴する**“歌モノの核”**として定着している。
10. 魂の居場所
歌詞に“自分の居場所”を強く謳う『魂の居場所』は、メンバーからファンへのメッセージがもっともダイレクトに届く一曲だ。演奏前に「ここがあなたの居場所であってほしい」と語られることもあり、イントロが始まる瞬間から特別な空気が会場を包み込む。演奏が進むと、客席から自然に「おーおーおー」とコールが湧き、ラストでは観客が「ららら〜」と口ずさみながら合唱する。このやり取りは定型ではないが、ファンとバンドの心が通じ合っていることを実感できる象徴的な場面だ。熱唱の合間にこうした声が重なることで、会場全体に温かな一体感が生まれ、静かな感動とともにじんわりと盛り上がる。演奏後もしばらく余韻が残り、“自分の魂の居場所はここだ”と胸に刻まれるような時間になる。マカロニえんぴつのライブにおいて、聴く人を強く結びつける核となる楽曲といえる。
11. ハートロッカー
アップテンポのロックナンバー『ハートロッカー』は、観客の手拍子による参加が定番化している一曲だ。イントロが鳴った瞬間から客席全体が一斉に手を叩き始め、リズムに合わせて会場がひとつになる光景は何度見ても圧巻。はっとりが手を挙げて合図を送ると、その瞬間に手拍子がピタリと揃い、観客は「音楽を一緒に作っている」という感覚を共有できる。さらに後半の「いいメロディーが〜」ではリズムが少し変化し、観客がタイミングを探りながら楽しそうに手拍子を打つ姿があちこちに見られる。まるでリズムゲームのように全員が参加できる仕掛けになっており、自然と笑顔が広がるのもこの曲ならではだ。演奏の勢いと観客のクラップが重なり合うことで熱量は一気に跳ね上がり、疾走感と多幸感を同時に味わえるライブの定番曲として定着している。
12. 遠心
**じわじわと熱を上げていく“ミドルの核”が『遠心』**だ。演奏が始まると客席は静かに耳を傾け、はっとりのソウルフルな歌声に引き込まれる。サビに差し掛かると一気に開放感が広がり、自然と手が高く掲げられる。さらにCメロでギアが上がると、フロア全体が熱を帯びていくのが体感できる。ラストでは拳を振り上げながら大歓声が巻き起こり、曲が持つ感情の高まりが会場を一つにする。フェスでも常連化しており、アリーナ規模の会場でもじんわりと熱を積み重ね、終盤には大きな渦を生み出す存在だ。SNSでは「泣き笑いしながら聴いた」「心に沁みる」といった声が寄せられており、演奏後には拍手とともに温かい一体感と深い余韻が広がる。派手さよりも“じっくり熱を育てる”魅力を持つ、マカロニえんぴつのライブを象徴する一曲である。
13. 月へ行こう
**幻想的な雰囲気をまとい、夜空に映える楽曲が『月へ行こう』**だ。筆者が体感した武道館公演では、大型LEDに浮かんだ“月”がラストで地球へ変化し、まるで宇宙旅行に出かけるような高揚感に包まれた。掛け声やコールはないが、静かなイントロから徐々に熱を増していく展開に合わせ、観客はじっと耳を傾ける。終盤に差し掛かると、ゆったりと拳が掲げられ、サビでは腕が左右に揺れてウェーブのように広がり、会場全体がひとつの星空に変わる瞬間が生まれる。SNSでも「宇宙に連れて行かれたようだった」という感想が見られるなど、体感型の演出と楽曲のスケール感が強く記憶に残る一曲だ。多くのセットリストで終盤前のブリッジとして配置され、景色を切り替え、次の爆発的な盛り上がりへとつなぐ役割も担っている。
14. 忘レナ唄
ピアノ主体のミディアムナンバー『忘レナ唄』は、ライブで披露されると会場全体をしっとりと包み込む。筆者が武道館で初めて体感したときも、背面スクリーンに切なさを映す映像演出が重なり、場内は一瞬で静寂に変わった。観客は誰一人声を発さず、歌詞にじっと耳を傾け、ラストでは自然にスタンディングオベーションが起こる。涙を拭う人の姿があちこちで見られたのも忘れられない光景だ。SNSには「泣きそうになった」「バンド全体が涙を誘う演奏だった」との感想が多く、ファンの心に深く残る一曲となっている。爆発的に盛り上げるタイプではないが、“静けさで観客を結びつける”特別な力を持ち、ライブの流れに奥行きを与える存在だ。
15. poole
紅茶花伝のCMソングとして知られる『poole』は、ミドルテンポの心地よいグルーヴが魅力だ。筆者がフェスで体感した際も、スイングする鍵盤に合わせて観客が自然と横に揺れ、会場にはリラックスした空気が広がっていた。決まった掛け声はないものの、サビに差し掛かると手が高く掲げられ、フロア全体が波打つような景色に変わる。会場によってはラストで自然発生的なシンガロングが起こり、柔らかな一体感を生むのも特徴だ。SNSでも「夏フェスで聴けるのが楽しみ」「グルーヴに浸れる」と好評で、比較的新しい曲ながら既に定番曲として浸透しつつある。さらに、『星が泳ぐ』や『なんでもないよ、』へのブリッジとして配置されると、ライブ全体をエモーショナルに仕上げる役割も果たす。横揺れ一択の心地よさと共鳴する景色こそ、この曲ならではのライブ体験だ。
16. Route 16
筆者が体感したライブでも、イントロから自然にクラップが湧き起こり、メンバーがそれに応えるように一節を即興で重ねる場面があった。その瞬間、会場はセッションのような多幸感に包まれ、「今ここでしか生まれない音楽」を全員で共有していた。観客はリズムに身を任せながら合間に手拍子を加え、演奏後には温かな拍手が会場を満たす。グルーヴを堪能し、バンドと観客が一体となる“一期一会のセッション”を味わえることこそ、『Route 16』がライブで特別視される理由だ。
17. 然らば
TVアニメ『アオのハコ』第2クールのOPに起用された『然らば』は、リリース直後からフェス常連入りを果たした新定番だ。筆者がMステでの生パフォーマンスを観たときも、鋭いギターリフと疾走感あふれるバンドアンサンブルが圧倒的で、青春の葛藤を描く歌詞と重なり胸を撃ち抜かれた。特に〈舞い切った千の夏と蒼、遮って蝶になった嘘〉というフレーズは、作品世界をそのまま音にしたかのようなリアリティがあった。ライブではロック色をさらに強めたアレンジで披露され、イントロが流れた瞬間にフロアがざわめき、拳が突き上がる。キメでは観客から「オイ!」という掛け声が自然に飛び、熱量が一気に加速していく。ジャンプとクラップが重なり合う爆発的な盛り上がりは、まさにフェス映えそのもの。アニメとライブの双方で強烈な存在感を放つ“新世代の代表曲”として、マカロニえんぴつの今を象徴している。
18. Mr.ウォーター
『Mr.ウォーター』は、ジャジーなイントロから一気にハードロックへ展開する“展開映え”チューン。筆者が初めて体感したライブでも、オルガンのような美しい音色に会場全体が静かに包まれ、その直後に炸裂する爆音に一瞬で空気が変わった。観客からは驚き混じりの歓声が湧き上がり、緊張と開放が交互に訪れるスリリングな時間が生まれる。コールが定型化しているわけではないが、ブレイクで自然と大歓声が走り、思わず声が漏れる瞬間が何度もあるのが特徴だ。メンバー自身も「ライブ映えする曲」と語っており、照明に照らされたバンドの力強い演奏と相まって、観客はその姿に見惚れる。SNSにも「イントロから一気に惹き込まれた」「照明とサウンドの相性が幻想的」といった感想が寄せられている。終盤はハードロック的な推進力で熱を一気に高めつつ、ラストは余韻を残して聴かせる構成。聴き入る静けさと爆発的な盛り上がりを同時に味わえる稀有な時間を作り出す一曲だ。
19. 恋のマジカルミステリー
『恋のマジカルミステリー』は、イントロから客席の手拍子が自然に沸き起こる“ライブ映え”のロックチューン。筆者が初めて聴いたときも、演奏が始まった瞬間にフロア全体から大きなクラップが巻き起こり、そのまま波のように広がっていった。昔ながらのアップビートなロックテイストが色濃く、観客は思い思いに体を揺らしたり、拳を突き上げたりと自由なノリで参加できる。決まったコールが用意されているわけではないが、サビ前後では自然と歓声が飛び、掛け声がリズムに絡むことで即興的な一体感が生まれるのも魅力だ。派手な演出がなくても、クラップと拳を突き上げる動作だけで圧倒的な熱気が場内を包むのは、この曲ならでは。フェスでは観客を一気に巻き込む切り札として、ホール公演ではライブ全体を引き締める“ロック魂”の象徴として存在感を発揮する。シンプルだからこそ強い、マカロニえんぴつのライブに欠かせない“熱源”のひとつだ。
20. だれもわるくない
『だれもわるくない』は「MAPPA STAGE 2023」のSpecial Opening Movieテーマソングとして初披露された楽曲で、映像とともに登場したときから強い存在感を放っていた。筆者も初めて聴いたとき、曲が進むにつれてどんどん楽器が重なっていき、音の厚みが増していく展開に一気に引き込まれた。
サビに入る瞬間の鳥肌は忘れられない。特に「大人の涙だぜ 君のその痛みに〜」というフレーズは、聴く者の胸をえぐるようで、それでいて優しく寄り添うような響きを持っている。SNSでも「引き込まれるように聴いた」「痛みを肯定してくれる歌詞に救われた」という感想が多く見られた。
痛みや弱さを抱えることを肯定してくれるような歌であり、大人になってから流す涙を思い起こさせる名バラード。『だれもわるくない』は、マカロニえんぴつのライブにおける“静かで強いクライマックス”を担う一曲となっている。
※PR:マカロニえんぴつ|チケットの相場を見る【チケットジャム】◇ まとめ|マカロニえんぴつ(マカえん)のライブで感じる“音楽と共鳴する時間”

マカロニえんぴつのライブは、ただ楽曲を披露する場ではありません。**歌詞が持つリアリティと、演奏の熱量、そして観客の声や手拍子が重なり合って初めて完成する“共鳴の時間”**です。筆者も現場で幾度となく体感してきましたが、あの一体感は音源では絶対に再現できないものです。
「なんでもないよ、」での大合唱は、観客一人ひとりの人生や感情が重なり合う奇跡の瞬間でしたし、「レモンパイ」「洗濯機と君とラヂオ」では拳を突き上げるコール&レスポンスが会場を熱狂の渦に包み込みます。一方で、「悲しみはバスに乗って」や「恋人ごっこ」では、誰も声を出さず、静けさと涙が支配する時間が広がる。“絶叫と沈黙の両方を味わえる”のがマカロニえんぴつのライブの最大の魅力といえるでしょう。
また、フェスとワンマンで見える表情の違いも特筆すべきです。フェスでは短時間で観客を引き込むため、「ブルーベリーナイツ」「ハートロッカー」のような瞬発力のある曲が前半から配置されます。ワンマンでは「魂の居場所」「月へ行こう」といった曲を軸に物語性が練られ、観客を深い世界観へと誘う。構成力の高さこそ、リピーターを増やし続ける理由です。
筆者自身、横浜スタジアム公演で「星が泳ぐ」とともに花火が打ち上がった瞬間を今も忘れられません。涙と歓声が入り混じり、夜空と音楽が一体となる体験は、音源だけでは絶対に届かない“現場の奇跡”でした。
今回紹介した20曲は、いずれもライブを語るうえで欠かせない定番です。もちろんセットリストは日々変わりますが、これらを知っておけば「どこで盛り上がり、どこで涙が溢れるか」を事前にイメージでき、初めての人もより深く楽しめます。
マカロニえんぴつの音楽は、あなた自身の物語と重なるときに最も輝く。 その輝きはライブという“生の場”でこそ実感できるものです。本記事がきっかけとなり、一人でも多くの人がステージを体感し、観客同士の声と感情が重なり合う奇跡の瞬間に立ち会えることを願っています。
◇ よくある質問(FAQ)
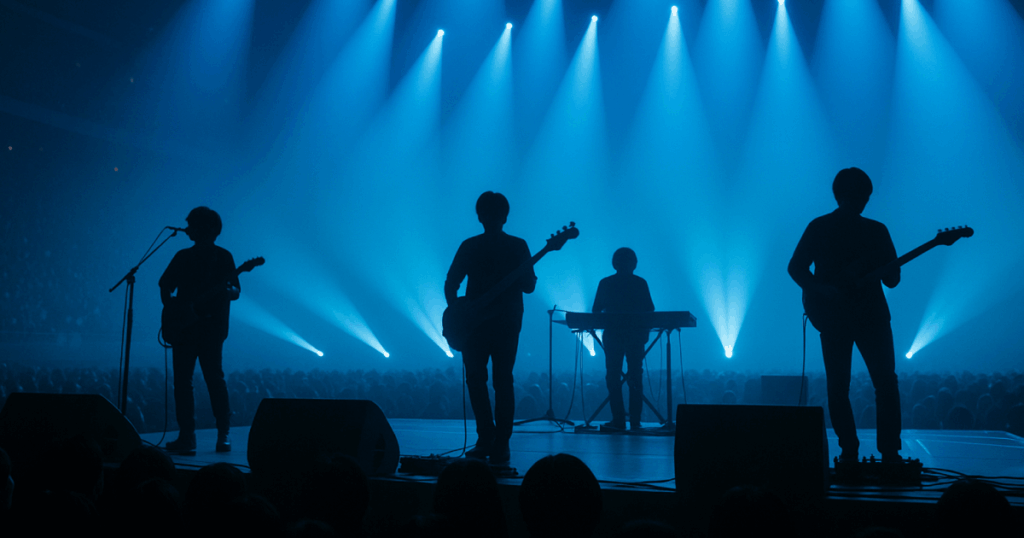
Q1. マカロニえんぴつのライブ初心者でも楽しめますか?
はい、初めての人でも十分に楽しめます。シンガロングが自然に起きる曲(「なんでもないよ、」「レモンパイ」など)や、じっくり聴き入る曲(「悲しみはバスに乗って」「恋人ごっこ」)がバランスよく組み込まれているため、声を出すのが苦手な人も、ただ聴くだけで感動できる時間があります。
Q2. フェスとワンマンライブで違いはありますか?
あります。フェスでは限られた時間で一気に会場を盛り上げるため、ロック色の強い曲が中心になります(例:「レモンパイ」「洗濯機と君とラヂオ」)。一方でワンマンライブはストーリー性を重視し、バラードや新曲も組み込まれるので、より深い世界観を楽しむことができます。
Q3. 定番曲は毎回同じですか?
定番曲は存在しますが、セットリストは公演ごとに変わります。例えば「なんでもないよ、」「ブルーベリーナイツ」などは高確率で演奏されますが、「Route 16」や「忘レナ唄」のようにレア枠でしか登場しない曲もあるため、どの公演に参加しても“その日だけの特別な体験”ができます。
Q4. 盛り上がる曲と静かに聴く曲の違いは?
盛り上がる曲は「レモンパイ」「ハートロッカー」など、手拍子やジャンプ、コールが起こる楽曲です。
静かに聴く曲は「恋人ごっこ」「悲しみはバスに乗って」「だれもわるくない」などで、声を出すのではなく歌詞と演奏に集中して涙する人も多いです。
Q5. これからマカロニえんぴつのライブに行くなら、予習すべき曲は?
特におすすめなのは、**「なんでもないよ、」「レモンパイ」「ブルーベリーナイツ」「星が泳ぐ」**の4曲です。これらはフェス・ワンマン問わず演奏される可能性が高く、ライブの一体感や感動を象徴する楽曲です。余裕があれば、今回紹介した20曲すべてをプレイリストに入れておくと安心です。
◇ マカロニえんぴつ(マカえん)公式サイト・SNSリンク一覧
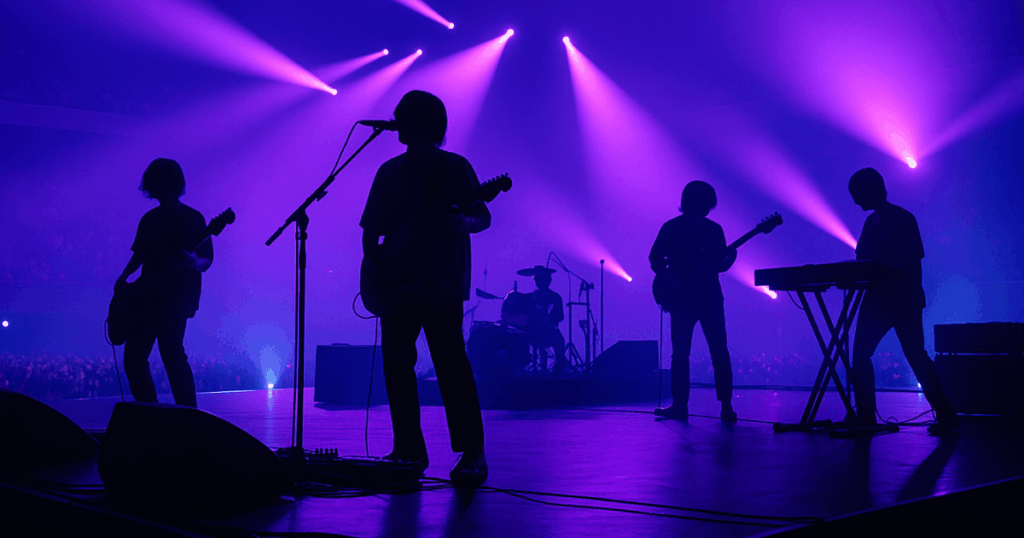
- Official Site(公式サイト)
https://macaroniempitsu.com/ - YouTube(公式チャンネル)
マカロニえんぴつ Official YouTube Channel - X(旧Twitter)
https://x.com/macarock0616 - Instagram
https://www.instagram.com/macaroniempitsu_official/